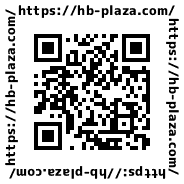>購入時の状態から旋条のツイストレートや条数を変更したりすると銃の特定が難しくなったりするものなのでしょうか。
新品の銃が使用された場合や銃身を交換した場合は施条痕のデータが無いため施条痕から銃を特定することができません。
例えば、事件Aで警察が入手した施条痕をデータベースから照合し、事件Bで入手した施条痕と一致すると事件Aと事件Bで同じ銃が使用されたことがわかります。
>散弾銃や大昔の前装銃のように旋条の刻まれていない銃によって事件が起こった場合、警察はどうやって凶器となった銃を発見するのでしょうか。
施条痕で照合できない場合でも、薬莢に残ったブリーチブロックフェイスやファイアリングピンによる傷、または火薬の成分から一致しているかを確認することが可能です。
ただ、それでも元データが必要になるため、必ずしも確実性の高い方法ではありません。
アメリカでは施条痕のデータベースはATFが管理していますが、このデータベースを利用していない法執行機関もあります。
関連記事:銃弾に刻まれる「施条痕 / 線条痕(せんじょうこん)」とは何か?